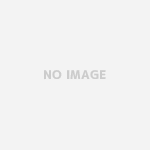秋から冬にかけて、空き巣や忍び込みなど、家屋に浸入を働く
「窃盗」が増えてきます。
こうした被害に遭わないための対策はできていますか?
ちょっとした隙で侵入被害に遭ってしまいますので
ポイントを少しまとめてみました。
侵入の原因
無締まり・ガラス破り
家族の安らぎの場であり、生活の基盤である住まいの防犯を
行なうことは非常に大切です。
住居などに浸入して盗みを働く「侵入窃盗」の現状は、
どうなっているでしょうか。
【 侵入窃盗 】
≪ 空き巣 ≫
家人が留守の家に浸入して金品などを奪う
≪ 忍び込み ≫
家人が寝ている間に浸入する
≪ 居空き ≫
家人が起きて過ごしている部屋とは別の場所に浸入する
現在、調べによると浸入窃盗の約7割が空き巣です。
十数年前まで、浸入窃盗の認知件数は増える傾向にありました。
当時、犯人が家に浸入する場所は、玄関などの出入り口が多数でした。
そこで官民挙げた防犯の合同会議が行われ、また、青色回転灯を
つけた自主パトロールなどの防犯ボランティアが活動して
対策が講じられました。
さらに、玄関のドアが破られないように強度を増したり、鍵穴を
ピッキング(特殊な工具を鍵穴に差し込んで開けること)されにくい
構造にしたりするなど、工夫を凝らしました。
防犯性能の高い建物部品が普及した結果、2002以降は浸入窃盗の
認知件数は減少し、出入り口からの侵入被害も減ってきました。
しかし、戸締りを忘れたり、ガラスを破られたりして被害に遭う
ケースは相変わらず多いのが現状。
浸入窃盗の犯人は、警報音などの「音」と、明るく照らされる「光」に
弱いといわれていましたが、近年はこれに顔や姿を監視される「目」、
浸入に時間がかかる「時間」が加わり、“犯罪防止4原則”になっています。
犯罪者に浸入を許す隙を作らないために、戸締りを忘れない
“ちょっとゴミ出しに”“ちょっと新聞を取りに”など少しの外出でも
『これくらいなら大丈夫』と思わず施錠する、近隣同士の普段からの
声かけ、家屋とその周りの整理整頓が非常に大切です。
整理整頓をしていない乱雑な環境は、犯人に浸入手段を提供してしまったり
足跡などを残りにくくしたりするため、浸入を招きやすくなります。
浸入窃盗による被害は金品にとどまらず、預金通帳やカードの盗難を
通して個人情報が開示される危険が生じます。
家人と鉢合わせになった犯人が強盗に変身したりするなど身体的危険も
伴います。
住まいの防犯に心掛け、安全・安心の環境づくりをしましょう。
被害に遭わないためのポイント
① 家の戸締りを忘れない
② 少しの外出でも施錠
③ 近隣同士の声かけ
④ 家屋と周囲の整理整頓
泥棒は、簡単に入り込めて、確実に窃盗でき、捕まらない、
この三つの条件がそろった家を探しています。
そのために道具を準備したり、下見をしたり、人目がつきにくい
家を探す、留守を確認するためにインターホンを鳴らしてみる、
しばらく見張ってみるなどの行動を繰り返します。
その時の服装は、普通の人と見分けがつきにくかったり、
普通のサラリーマンと変わらない服装、バッグなどを持っていたり
しますので注意しましょう。
また、犯人が浸入を試みてから諦めるまでの時間は、5分以内が
全体の69%に上ります。
そのため、家屋が“5分間を耐える”ようにすることが大切です。
日本防犯設備協会
https://www.ssaj.or.jp/
犯人はどんな時にあきらめる?
近所の人にジロジロ見られる
侵入者は、「近所付き合いが良く、連帯感のある住宅街を嫌います。
犯行をあきらめた理由で多いのは、「近所の人に声を掛けられたり、
ジロジロ見られたりした」こと。
あきらめた理由全体の63%にも及び、最も効果があるといわれています。
不審者を見かけたら、まずは「何か御用ですか?」などと声を掛けましょう。
日頃から近所付き合いを大切にすることが、犯罪に強いまちづくりにつながります。
ドアや窓に補助錠が付いていた
ドアや窓に補助錠が付いている場合、浸入までの時間を稼ぐことができ、
結果として犯行をあきらめさせることができます。
窓やドアは、一つに対して二つの鍵を掛ける「ワンドア・ツーロック」を
原則にしましょう。
警察庁などの3省庁と民間団体では、鍵を破壊する被害を防ぐため、
強度が高い、また解錠されにくい製品であることを示す防犯性能の
高い建物部品(CP部品)を選定。
また、窓枠に取付け、上枠と窓枠とを締め付け固定する補助錠や
引き違い窓のガラスに貼り付けて、窓が開かないようにするものもあります。
防犯カメラが付いていた
防犯カメラの設置も、泥棒に浸入をあきらめさせる力になります。
防犯カメラは、疲れない・眠らない(作動し続ける)、見逃さない、
忘れない(データが保存できる)ことが大きな特徴です。
防犯をするべき範囲をくまなく見守るカメラは防犯抑止効果を高めます。
飼い犬がいた
家人が飼っている犬がいることで、浸入をあきらめた場合も、あきらめた
理由全体の31%に上っています。
犬に吠えられると犯行がしにくいため、飼い犬がいない住宅を選ぶのです。
ただし、家人が吠え声に気付かなかったり、侵入者が手なずけてしまったり
する場合もあるため、過信は禁物です。
浸入警報システムが付いていた
塀の上などに設置されて、侵入者に目を光らせる赤外線センサー、侵入者を
検知すると大きな音で威嚇する浸入警報システムなどは、夜間や人通りの
少ない場所で効果を発揮します。
システムでは、最も守りたいものを囲む警戒線から、順次外に広げるように
設計し、侵入者の情報をいち早くキャッチし、威嚇します。
窓に頑丈な面格子が付いていた
トイレや浴室などの高窓。
高い位置にあるからといって、安心していませんか?
防犯性能の低いサッシやガラスでは、破壊され簡単に浸入を許してしまいます。
そうしたとき、窓に頑丈な面格子が付いていれば、浸入を防ぐことができます。
窓の下に、浸入を容易にしてしまうような足場になるものを置かないことも
心掛けてください。
パトロール中の警察官に出会った
パトロール中の警察官に出会うことで、浸入をあきらめる効果は高いとされ、
断念する理由の20%を占めています。
警察では「良好な治安は、社会・経済の発展の礎」として地域社会などと
連携しながら地域パトロールを行うなど、浸入窃盗を含めた犯罪を
なくすための努力をしているそうです。
窓などに合わせガラスが入っていた
浸入を許してしまった原因として、戸締りの忘れに次いで多いのが
「ガラス破り」、そんなときに有効なのが「合わせガラス」。
このうち、2枚のガラスの間に、0.76㍉以上の厚さの、強靭な特殊
フィルムを密着させたものを「防犯ガラス」といい、窓の鍵を開ける
だけの小さな穴も開きにくいため、大きな防犯効果が期待できます。
こんなことにも注意!
泥棒は「ゴミの日」をチェックする
浸入窃盗の抑止に最も効果があるといわれる地域住民の『目』。
では、泥棒は地域のどんな様子を見て、住民が見知らぬ人に注意を
払っていると感じるのでしょうか。
そのポイントは、ごみ。
指定日以外にゴミがでているかどうかをチェックします。
「ゴミの日」が守られていない地域では、地域の一体性が損なわれており、
侵入者に安心感を与えるといいます。
また、犯罪者は、犯行後に逃げることを考え、駅に近いか、立ち話を
している人がいないか、通行人が少ないかなどをチェックしています。
人の目は、住まいの防犯にとって大きな力をもっています。
植栽などの目隠しは防犯に逆効果
一戸建て住宅などの場合、一見、泥棒が入りにくそうな高い塀や
生い茂った植栽。
プライバシー保護にも役立ちそうですが、その半面、不審者が一度
敷地内に入ってしまえば周囲から見えにくいため、泥棒にとって
格好の目隠しになってしまいます。
住宅への侵入作業に時間をかけることができ、被害に遭いやすい
環境を作ってしまいのです。
なるべく塀を低くしたり、敷地内が見えるように囲いを格子状に
したりすることが大切です。
また、植栽はせん定をして死角を作らず、見通しをよくしましょう。
周囲からの見通しを遮る物を置くのも防犯上危険です。