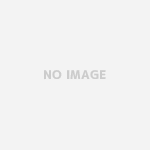近年、アナログレコードの人気が復活してきている。
扱いに手間が掛かる面もありますが、
それが逆に魅力という人も。
レコードの人気
音の深み、温かみに共感
音楽を聴く方法には、CDはもちろんのこと、スマートフォンに
音楽をダウンロードして持ち歩くなど、さまざまな手段があります。
そうした中、愛聴者数が伸びているのがアナログレコードの使用です。
アナログレコードが、なぜ今?人気を集めているのでしょうか。
一般社団法人「日本レコード協会」の広報部によると日本での
アナログレコード生産枚数は1970年代後半が特に多く、直径17㌢の
レコードは、79年に1億1000万枚も生産。
直径25㌢と30㌢のレコードも78年に約9300万枚と、ほぼ国民
一人に一枚の割合に達しています。
ところが82年にCDが発売されると、CDの生産枚数が急増し、逆に
アナログレコードは減少。
87年には生産金額でCDがアナログレコードを抜きました。
その後もレコードの枚数は減少し続け、90年後半には、CDの生産枚数の
100分の1未満になってしまいました。
こうした状況に変化が現れたのが2008年。
アメリカでアナログレコードを見直す企画「レコード・ストア・デイ」が
開催され大きな反響を呼びました。
以降、世界各地で開催されるようになり、日本でも11年から開催。
このころからアナログレコードが再評価されるようになり、生産量が
増加するようになりました。
また、”アナログレコード世代”だけでなく、若い世代のアーティストにも
レコード制作の動きが広がるほか、新たにアナログレコード店がオープン
するケースもあります。
人気の秘密は「音に深みがある」「人間が奏でて歌う温かみを感じる」との
感想もあります。
レコードの復活の話題自体が人気の相乗効果を呼んでいる面もあります。
また、レコードジャケットを観賞用に飾る楽しみや、珍しい音源を収集すること、
レコード盤や針の手入れなどが必要な”手間”に人間味を感じるなど様々な
楽しみ方があり、着実に人気が広がっているレコード。
その動きはまだまだ続きそうです。
訪ねてみよう
金沢蓄音器館
レコードの歴史は古く、約160年に及ぶといわれます。
電気が一般的ではなかった時代、電気を使わず録音した音声を再生させた
道具が「蓄音器」。
この蓄音器を収集・展示すろ施設に一つが、金沢市内にある「金沢蓄音器館」。
トーマス・エンジンが1877年に蝋(ろう)を使った筒状レコードの実験
再生に成功し、蓄音器の普及が始まりました。
当館には、蝋管用の蓄音器や、平円盤式に変わったレコードの蓄音器など、
600台以上を収蔵し、常時150台を展示しています。
蓄音器、SP盤は全国から寄贈され、レコードは3万枚を超えると言っています。
1階では、月に数回テーマに沿ったレコード盤の観賞会や、ゲストを招いての
ミニコンサートなどを開催。
2階には、エジソンの発明した蓄音器から発展した各種の蓄音器を聴き比べる
実演コーナーもあります。
3階には明治、大正、昭和の各時代に活躍した蓄音器の数々を、時代を追って
展示するなど多彩に。
聞き比べの実演は1日3回行われますが、「1分78回転のSPレコードは、
聴くたびに音の溝がすり減っていくため、蓄音器による再生は貴重な体験」と
館長が語っている。
詳細
http://www.kanazawa-museum.jp/chikuonki/